|
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
試合会場  「さぁお待たせいたしました! Aブロック第2試合、ドイツ代表ウィータ選手と、日本代表木ノ内美佳選手の対決です。さっきまでばばぁ……失礼、西園寺さんがいらしゃったのですが、何でも『必殺! 暴れん坊黄門・はぐれ侍純情派スペシャル』を見るため退席されたので、再び実況は私、実況子がお送りいたします!」 「さぁお待たせいたしました! Aブロック第2試合、ドイツ代表ウィータ選手と、日本代表木ノ内美佳選手の対決です。さっきまでばばぁ……失礼、西園寺さんがいらしゃったのですが、何でも『必殺! 暴れん坊黄門・はぐれ侍純情派スペシャル』を見るため退席されたので、再び実況は私、実況子がお送りいたします!」試合時間到来。すでに入場を済ませた両サイドは、闘技場の上でにらみ合いを続けていた。 簡単なチェックと説明が済んだ後、説明役が闘技場から降りていく。このメイドファイトに限って言えば、レフリーなど無用なのだ。  「さぁ準備は万端! 一度は収まりかけたボルテージも再び高まってきたぁ! それでは早速参りましょう。Aブロック第2試合! メイドファイトぉ! レディィィィ……ゴォォォォッ!」 「さぁ準備は万端! 一度は収まりかけたボルテージも再び高まってきたぁ! それでは早速参りましょう。Aブロック第2試合! メイドファイトぉ! レディィィィ……ゴォォォォッ!」況子の実況と同時に、試合のゴングは鳴らされた。 「速攻で決めてやる!」 すぐさま動いたのは右手をかざしたウィータだった。その掌の指と指の間には小さな鉄球が挟まれている。彼女はそれをほおると、いくつも眼前に展開させた。 「っ!?」 いきなりの行為に戸惑う美佳。しかしウィータは構わず、それらの鉄球にハンマーを横殴りに弾き飛ばした。 『Schwalbefliegen』 ウィータの手持ちのフリューゲルアイゼンが、その名を告げる。弾かれ、赤い光を帯びた鉄球は、各方向から美佳へと弾丸のように襲い掛かっていく。 「こんなもんっ!」 しかし美佳は冷静に手刀を振るい、正確に鉄球を叩き落した。 「だろうなっ!」 「なっ!?」 だが、それにより動きを止められた美佳には目もくれず、一気にウィータは美佳の主人である陽一のもとに駆け込んでいく。 「できるだけ傷つけねぇで済ますなら、一気に勝負を決めるのが基本! その薔薇、もらう!」 「くっ!」 完全に不意をつかれた陽一は、対応が遅れた。ウィータの手がまっすぐと胸につけられた薔薇に伸び―― 「――っ!?」 「そう簡単には……終わらないよ」 その手を、いつしか鉄球の雨をすべて砕いていた美佳がつかんでいた。 「はえぇ……。やるな」 さすがにウィータも少し驚いた。鉄球をすべて粉砕し、勢いをつけて手を伸ばした自分の手をつかんでくるとは、正直思いもしなかったのだ。 「あなたの考え方も理解できるけどね」 美佳はつかんだ手をひねるように、ウィータを空中に投げ飛ばす。 「わたしとしてはまず、主人は度外視で戦いたいわけ……よ!」 そして、落下地点に狙いを定め、気合をこめた正拳突きを解き放った。 『Panzerschild!』 瞬間、アイゼンが光る。同時に、彼女の前面に魔法結界が展開され、その拳を止めていた。 「主人を度外視……だと?」 「そ。やるからには正々堂々、お互いに足かせなしで! ――まずはわたしを倒さないと、おっちゃん……もとい! ご主人様のもとへは行かせないってことよ。あなたもそれが望みでしょ?」 「あ……」 そこで初めてウィータは気がついた。 主人への攻撃は確かに理にかなうかもしれない。しかし、そのせいで自分の大切な主であるソフィーは無防備になる。相手によっては、ためらいもなくソフィーを殺してくるかもしれないのに……。 (迂闊だった……な。相手に救われるとは) 思わずウィータは舌打ちする。 ウィータの態度に、自分の思惑が通じたと判断した美佳は、にまりと笑みを浮かべた。 「どお?」 「上等!」 結界を解除し、間合いを取ったウィータ。 「なら、おめーを気絶させるだけだ! 『テートリヒ・シュラーク!』」 追撃がないのを知ると、再びフリューゲルアイゼンを振りかざし、美佳に迫る。 「木ノ内君!」 「あいよ!」 ウィータは見た。 アイゼンを振り下ろす直前に、美佳が主人から何かを受け取ったのを。 そして、その受け取ったもので…… 「――受け止めただとぉ!?」 陽一が投げ渡したのは木刀。受け取った美佳は、しっかりとウィータの強力な一撃を受け止めていたのだ。 「アイゼンの攻撃を、たかが木の棒ごときで!?」 驚愕するウィータに、美佳は口元に不敵な笑みを浮かべた。 「魂が入ってるこの木刀は、ただの木の棒じゃない! どんな真剣よりも強く――折れない!」 「いや、ただの木刀じゃないし」 思わず突っ込む陽一。 陽一が投げ渡したのは、MFDが特殊開発した木刀。木刀と言うが、実はセラミック製。しかも強化コーティングを施しているもので、その強靭さは日本の科学力のすべてにおいて保障されていた。 そんな事情を知らない……いや、知っていたとしても、ウィータは驚愕を隠せなかった。砕けないものはないといわれたフリューゲルアイゼンの一撃を止められるなんてことなど、想定外だったのだから。 その驚愕が、相手に好機を与えた。美佳の気合とともに、木刀がハンマーを押し返す。 「反撃!」 ウィータが態勢を崩したところで、一気に美佳が前に出た。 「動きは見えてる! ――木ノ内君! 3時方向に突きだ!」 「おうっ!」 陽一の指示を受けた美佳が、何のためらいもなくその支持通りに一撃を繰り出す。 「ぐぅっ!?」 そこ意外なら回避も防御もできたウィータであったが、完全に死角をつかれ、まともに食らった彼女は、思わずうめいた。 「後方に下がる! そのまま追撃で振り切れ!」 「抜き胴ぉぉぉぉっ!」 さらに連続攻撃がうなった。陽一の指示通りに動く美佳の鋭い攻撃が、ウィータが結界を張るよりも早く決まっていく。まるで完全に動きを見切られているかのように。 「ウィータ!」 後ろで見てるだけしかできないソフィーが、思わず叫んだ。 その声が、やられっぱなしのウィータの脱出口となった。 「くっ……。――痛く……ねぇっ!」 瞬間的に身体を集中させ、再び単発の「シュヴァルベフリーゲン」を解き放ち牽制する。さすがに気を取られた美佳のその隙に、大きくバックステップを踏んで間合いを取り、何とか連続攻撃から逃れた。 「ウィータ! 大丈夫か!? ウィータ!!!」 自分の近くに来たウィータの身体を支えつつ、ソフィーが声を荒げた。 「あぁ、大丈夫だよ、ソフィー。こんなの、ちっとも痛くねぇ」 いつの間にか額から流れてる血を拭いながら、健気に主人であるソフィーに微笑むウィータ。心配をかけたくない思いでいっぱいだが、残念ながらソフィーの表情は晴れない。 「ウィータ、もうえぇ。降参しよ。うちは傷つくウィータのそんな姿、見とぉない!」 「大丈夫だって。――鉄槌のメイド・ウィータと、鉄の翼『Flügel Eisen』は、こんなことで引きはしねぇ」 (と言ったものの……やべぇな) 精一杯強がって、笑顔を見せ続けるウィータだが、状況は芳しくない。 (あの男の指示通り的確な攻撃をしてきやがる。それに、アイゼンの一撃を受けてヒビひとつ入らねぇところを見ると、あの木刀にも仕掛けがあると見ていいし……) ソフィーの手を振りほどき、気丈に身構えるウィータ。厳しい視線で、美佳をにらむ。 (となると、それ以上の破壊力が必要ってことか……。フルドライブのギガント……行くしかねぇか!?) フリューゲルアイゼンのフルドライブ・フォルムであるギガント・フォルム。これなら破壊力は格段に上がり、あの木刀を防御ごと撃ち砕くこともできるだろう。 (これなら……) 「あかんよ! ウィータ!」 そう決意を固めるウィータの肩に、ソフィーが手を置いた。 「ソフィー……?」 振り返ったウィータに、ソフィーは静かに首を振る。 《フルドライブはあかんよ、ウィータ》 そして、脳内に直接語りかける思念通話で、ウィータに話しかけた。 《ソフィー? 何で!?》 いきなりの思念通話にも驚かず、ウィータも思念で答える。 ウィータとしては、もう残された手段はフルドライブしかない。それを止められるとは思わなかったのだ。思念通話とはいえ、思わず声を荒げてしまう。 そんなウィータに、ソフィーは静かに首を振った。 《確かに相手の動きは鋭くて的確や。せやけど、それは攻撃力だけの話で、防御力は普通の人と変わらへん。そんな相手にフルドライブの攻撃をしたら……》 《だけどソフィー! このままじゃ、負けてしまう!》 《負けてもえぇよ。うちは構わん》 はっきりと、ソフィーは答えた。 わかっていた。この優しき主は、他人が苦しむのを望まない。自分のためなら他人なんてどうでもいいとは決して思わない。だからこんな状況になれば、迷いなく降参するだろう。 負けることで、ソフィーが望む今の平穏な暮らしが失われることはない。だから迷いも無い。 わかってはいるが……。 《ソフィー……っ!》 納得はいかない。 今は失わないかもしれない。しかし、未来は? ソフィーの病気が治らない限り、彼女に未来はないはず。 それを守りたい。それだけが望みなのに。 《…………》 だが、主の望みは絶対。それに従うのが、ベルマのメイドたる自分の使命。ウィータは唇をかんだ。 《――せやけどな》 そんなウィータに優しくささやきかける声。 《鉄槌のメイド・ウィータと、鉄の翼『Flügel Eisen』に砕けないものはあらへん……。そやろ?》 《……? ソフィー?》 《うちに対する想いはええねん。でも、純粋にウィータは負けるのがイヤなんやろ? ほんま、負けず嫌いなんやから》 くすくすと笑みをこぼすソフィー。 《フルドライブは危険やから許可できへんけど……それ以外で思いっきりやるのはえぇ。メイドたちの願いをかなえるのは主の務めや。勝っても負けてもえぇ。最後には笑いあってる勝負にしよ》 そして、まっすぐな瞳でウィータを見つめる。その眼差しは信頼の証。 《うん……わかった》 忘れてた。この主は、すべて理解してくれていることに。 ふっと、本当に痛みが消えた。 (負けねぇ。フルドライブを使わなくても勝てる! ――ソフィーが信頼してくれるなら!!) (迷いが……消えた?) 身構えるものの、一歩も動かないウィータに対し、美佳も身構えたまま動かず、じっと彼女を見つめていた。 その彼女から、迷いの気配が消えた。何か意志をかためたようだ。 「一気に、攻勢をかけてくるかもしれんな」 後ろでぽつりと陽一がつぶやく。 「データによれば、フルドライブと呼ばれる破壊の鉄槌があるとされている。詳細なデータはわからないが……間違いなく攻撃力は上がってくる」 「うん」 「その特殊木刀も、どこまで耐えられるかわからん。勝負は早めにつけないと」 「……負けるって?」 その陽一の言葉に、美佳は鼻で笑った。 「このわたしが、負けると?」 「…………?」 珍しく自信過剰な物言いをする美佳に、陽一は眉をひそめた。 こんな言い方をする子ではなかったはずだ。初めての本番に少しテンションが上がってるせいもあるかもしれないが、それにしては……。 「負けるわけないじゃん」 首をかしげる陽一に、顔だけ彼に向けて、彼女らしい笑みを浮かべた。 「だって、おっちゃんが指示をくれてんだよ?」 「っ!」 「おっちゃんの指示ね、確かに的確だわ。このMFに参加するためにいろいろ組んでやってきたけど、身体が納得してる」 再び顔をウィータに戻すものの、言葉は続ける美佳。 「最初は興味本位だったけどさ、今は楽しくて仕方ないよ。ある意味、会社も刺激的だったけど……こっちの方が燃えるよ。メイド燃え~なんて言葉も、今なら納得できるかな。うん」 「いや……その言葉は漢字が違うと思うぞ」 思わずため息をついてしまう陽一。 しかし、彼女がいきなり本音を語りだすとは思わなかった。初めての試合に、興奮しているのもあるのだろうが。 「まぁ……その言葉を聞けたのは、少し嬉しいかもな」 ため息交じりとはいえ、つい笑みがこぼれてしまう。彼女が聞かせてくれた信頼の言葉。いろいろ苦労させられた、少し困ったメイドだが、充分にこたえてくれていたのだ。 「じゃ、勝たないとな。ほしいものがあるんだろ?」 「ん」 「せいぜい、国が用意できるものでよろしく頼むよ」 「大丈夫。『おっちゃんなら』用意できるよ?」 「は?」 「だいじょ~ぶ、まっかせて~」 いつもの決まり文句が出た。 「あの子が何を仕掛けてくるかはわかんないけど、それも撃ち砕く。二の太刀いらずでね」 それを最後に―― 美佳の身体から、気合が激しく膨れ上がっていった。  「さぁ両者からの気合が存分に立ち上がる! 膨れ上がった気配に緊張感が高まり、会場も静まり返った! 次の一撃で勝負が決まりそうです! 果たして勝利の女神はどちらに微笑むのかぁっ!?」 「さぁ両者からの気合が存分に立ち上がる! 膨れ上がった気配に緊張感が高まり、会場も静まり返った! 次の一撃で勝負が決まりそうです! 果たして勝利の女神はどちらに微笑むのかぁっ!?」況子のナレーションが響き渡る。 その言葉通り、両者からは異様な気配が立ち上がっていた。 ウィータはハンマーを右手に持ったまま、左手に魔力の塊を作り―― 美佳は両手に持つ木刀に全身の気合をこめて―― ただ静かに対峙していた。 「……ウィータ……」 「……木ノ内くん……」 緊迫感が高まり、二人の主人であるソフィーと陽一も、介入することができない。 しばらくその光景が続き……誰かが息を呑む。 「――っ!」 刹那、俊敏な動きを見せて、美佳が動いた。全ての気合を木刀にこめ、一直線に。余りのスピードに、例え身構えていてもウィータに回避や防御をする手段は残されていないほど。 だが、関係なかった。 ウィータにとって、回避も防御もする気などなかったのだから。 「吼えろ! アイゼン!」 一撃が決まる直前、ウィータは左手に溜めていた魔力の塊に、自らのハンマーをぶつけた。 『Eisengeheul!』 アイゼンが光ると同時に、魔力光に接触。瞬間―― 「……っ!?」 物凄い音と光が撒き散らされた。直接的なダメージはないが、並みの人間ならこれだけで気絶ものである。それを至近距離で美佳はモロに食らってしまった。 「しまっ!」 完全にウィータの姿を見失う。相手の技が発動する前に振り下ろした木刀から、わずかに手ごたえはあった。直前に張ったと思われる結界すら破壊したはずだ。 しかし、倒した手ごたえは……ない。 「上だ!」 耳鳴りがひどい中、陽一の声だけは聞こえた。反射的に反応し見上げると、先ほどの一撃で吹き飛んだのか、赤い帽子をなくしたままのウィータが頭上にいた。 「アイゼン! フォルムツヴァイ!」 『Raketenform!』 ウィータが吼えると同時に、ハンマーの形状が変わった。片方がロケットの推進口のようなものに、そしてもう片方がスパイクの形に。 「砕け!」 『Explosion!』 そのハンマーの柄から、弾丸の薬莢のようなものが飛び落ちていく。アイゼンに込められた魔力カートリッジを消費することで、一時的に破壊力を増すシステムを持つのが、アームドデバイスの特徴。それは今回もいかんなく発揮した。 「ラケーテン……ハンマーぁぁぁぁぁっ!」 そして、そのまま空中でハンマー投げのような勢いで回転し勢いをつけたウィータは、推進口から放たれた噴射エネルギーの力も借り、スパイクを美佳にたたきつけた。 「甘いっ!」 しかし、ここで美佳も驚嘆すべき対応に出た。 わずかばかりの一点しかないスパイクの先を、木刀で受け止めたのだ。 「これくらい、見切れないとでも……っ!」 「思わねぇ!」 受け止められたはずのウィータは、しかしそれでも力をこめる。 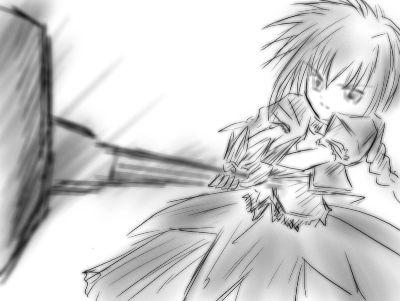 「アイゼン! ぶっ潰せぇぇぇぇぇっ!」 『Jawohl!』 アイゼンが光り、噴射口から噴出すエネルギーが増す。それにより、スパイクの先が徐々に木刀に食い込んでいく。 やがて、セラミック製のその木刀に亀裂が走り―― キィィィィィン! 「きゃっ!?」 甲高い音とともに、木刀が粉々に砕け散る。受け止めていたものがなくなったアイゼンは、その勢いのまま振りぬかれ、美佳に直撃した。 わずかな悲鳴を上げて、美佳は闘技場にたたきつけられる。 「木ノ内くん!」 思わず陽一が声を上げた。 失策だった。あそこまで追い詰められ、逆転するにはフルドライブしかないと読んでいた陽一は、ためらいもなく美佳に攻撃を許可した。フルドライブが発動し攻撃に来ても、俊敏さでは美佳が上。なら先に美佳の一の太刀が決まっていたはずだった。 だが、ここで冷静にフルドライブを発動させず、ぎりぎりまで引きつけてからの視覚撹乱攻撃に来るとは。光と音を撒き散らされ、相手の動きを見ることも、的確な指示を出すことも阻害されてしまい、美佳の反応が遅れた。 一の太刀の選択もミスだった。二の太刀いらずといわれたその威力は確かに絶大だが、その分隙も大きい。むしろあそこから防御できたのは奇跡に近いし、美佳の反射神経を褒めるべきだろう。だがもうひとつ余裕があり、回避することができていれば、勝利は間違いなく美佳のものだったはずだ。 勝ちを急ぎすぎた。完全に自分のミスだった。 「――終わりだ」 美佳の一撃を完全に交わしきれず、かすった程度なのに、いまだ衝撃が残る。しかしウィータは意識をしっかりと保ち、陽一にアイゼンを向けた。 「その薔薇、渡してもらう」 「待った!!」 しかしそのウィータを制するものがいた。 陽一ではない。背後の、主であるソフィーの近くにいたもの。 「チェックメイトはこちらが先。自分の主を傷つけられたくなかったら、おとなしく降参していただきます」 営業の口調に切り替わった美佳だった。 倒れてそのまま気絶しているはずなのに、即座に回復したのか、俊敏に動きソフィーの近くにいたのだ。どこからか取り出した特殊警棒を片手に、ソフィーの身体を捕縛していた。 このままなら、距離的に美佳の方が有利。よもやの逆転劇に、観客全員が息を呑む。 「……何の冗談だ?」 しかしウィータは平然とした態度で、美佳の方に振り向きもせずに告げた。 「この期に及んで……まだあたしを試そうというのか? 舐めんじゃねーぞ?」 「それはどうかしら。わたしは勝つためなら……」 「へたくそなんだよ、おめーの演技。バレバレだっつーの」 はぁと肩をすくめながら、ウィータは振り返る。 「それともこう言わせたいのか? 『あたしの知ってるキノウチミカは、自らが決めたルールを破るヤツじゃねぇ』なんて、くだんねーことを」 不敵に浮かべた笑み。動揺を隠そうとしたものではない。明らかにわかりきった表情。 「……バレてるみたいですよ?」 身の危険に曝されてるはずのソフィーも、笑顔で美佳に告げる。 「だそうだ」 そして陽一からも、ため息混じりにとどめの言葉が放たれた。 ソフィーにも陽一にも、いきなりの美佳の行動を看破している物言いだった。 「――ちぇっ」 くすっと笑みをこぼし、美佳は特殊警棒を投げ捨てる。 「少しは動揺したりするかな~とか思ってたのに。これじゃ、わたしにいいとこないじゃない。せっかく『わたしは約束を破る女じゃない』とか言って、颯爽と立ち去ろうと思ったのにぃ」 口調もいつものものに戻り、けらけらと笑う美佳。 「少しはガキんちょらしく、焦れっつーの」 「……おめーに言われたかねぇ」 「あーっ! 勘違いしてるわね? わたしはこう見えても24を越えてるのよ!? ちょっとは敬いなさいよね!」 「ふん、やっぱガキはてめーだ」 むくれる美佳に、ウィータはアイゼンを肩に担ぎ、ちょっと意地悪な笑みを浮かべた。 「たかだか24年じゃねーか。……あたしは数千年以上生きてるし」 「はぁ? す、数千年!? その姿で!?」 美佳もさすがに驚いた。外見だけ考えても、自分より幼く見えるこの少女が、数千年? 「だから敬え。いーな」 目を丸くする美佳に、ニヤリとウィータ笑みを浮かべてそう告げた。  「勝負あり! 勝者! ドイツ代表、ウィータ選手!!」 「勝負あり! 勝者! ドイツ代表、ウィータ選手!!」陽一から手渡される形でウィータが薔薇を手に取った瞬間、況子は高らかに宣言した。と、同時に、会場が一斉に沸きあがった。 その喝采など気にも留めず、ウィータはソフィーのもとに駆け寄った。 「ソフィー! 勝ったよ! 見ててくれたか?」 「あぁ見たで。……ったくもう、ぼろぼろやないか」 ソフィーはハンカチを取り出し、ウィータの顔ににじみ出る血を拭い取った。 「でも、約束、守ってくれたな」 そして、優しげに微笑んだ。 「ウィータも木ノ内さんも、えぇ笑顔やったで」 「今のソフィーもな」 「そか? ……じゃ、うちも約束を守る。今日は腕に寄りをかけるからな」 「やった~。ソフィーのメシはギガウマだしなー」 仲むつまじい主とメイド。ドイツ代表の二人の姿を、陽一は見つめていた。 「……あぁして見ると、年相応な少女という感じがするんだがな。主の前だけは、本来の姿……というわけか」 ぽつりと呟くと、同じく傷だらけの自分のメイドを出迎える。 「ごめん、おっちゃん。負けちゃった」 「仕方ない。あれは私の判断ミスだ。君の責任ではないよ」 苦笑交じりに陽一は言う。 何だかんだと言って、正直畑違いのこの大会で美佳は最善を尽くしてくれた。彼女を責める理由はどこにもない。 ――まぁ、自分はMFDの上司からさんざん苦情を言われるかもしれないが。 「いや良くない!」 いろいろ覚悟を決めかけていた陽一に、しかし美佳は告げた。 「一度引き受けた仕事は完遂して当たり前。それができなかったわけだし……わたしも上への報告にはついていく」 「木ノ内君……」 「木刀の耐久性だとか、相手情報の不足とか、いろいろ難癖つけて反撃してあげるから。だいじょ~ぶ、まっかせて~」 「いや、まぁ、その……お手柔らかに……」 どうやら、もう少しこの困ったメイドさんのフォローをしなくてはならないようだ。 別の意味で、未来がどんよりな板倉陽一である。 「……と、そういえば」 そこでふと陽一は思い出した。 「結局、本当にほしいものって何だったんだ? 結局優勝できなかったから、かなえることはできないが」 「ん~?」 陽一が疑問に思っていた、美佳が本当にほしかったものとはいったい何なのか? 「かなわないことないよ。おっちゃんが協力してくれれば。報酬でもいいんだけど?」 「私個人でか? 借金など背負いたくないんだが」 「あはは、そんなもんじゃないよ」 ひとしきり笑った後、2・3歩彼の前に歩き、そして振り返ってこう告げた。 「ま、後で教えてあげるよ。――それまでは秘密♪」 ころころとした、可愛らしい笑顔とともに。 その表情に、不覚にも陽一は何も返すことができなかった。 ただ。 (やっぱ、詐欺だよな) 心の中で、一言付け加えて。 (あの実年齢とは異なる、体格に見合った笑顔と言うのは) |
||||||||||||||||||||||
maid fight Aブロック第2試合 終わり |
||||||||||||||||||||||



