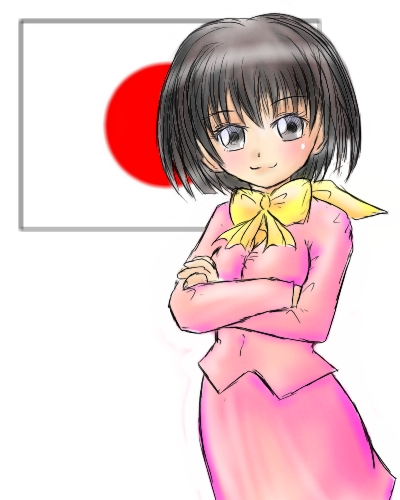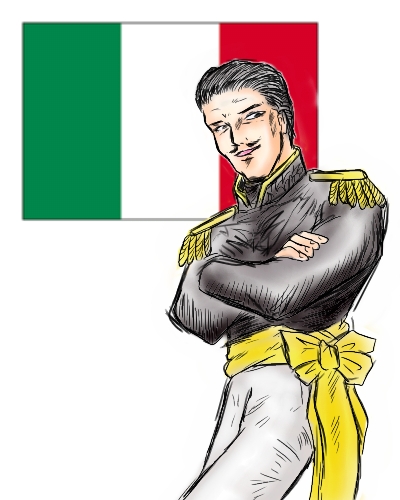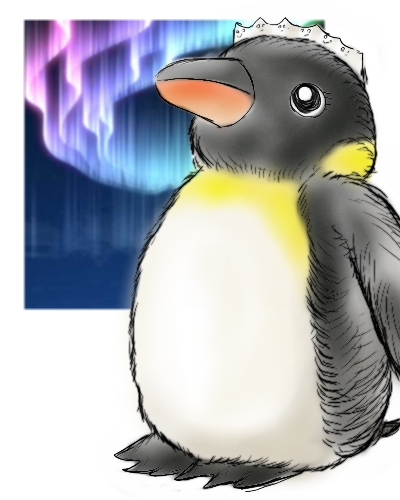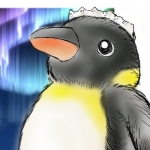セーシェル共和国代表 伏魔殿邪美  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「………………」 伏魔殿邪美は、非常に困惑した表情でため息をついた。 クールビューティな顔立ちながらも、どこか優しげなオーラ。しかもかなりの美人。普通の姿なら、誰もが感嘆の吐息を漏らすだろう。 しかし、今彼女が着ているのはメイド服。何らオリジナルのデザインはない。オーソドックなメイド姿なのである。定番のホワイトブリムを頭につけ、黒と白のエプロンドレス……というよりはフレンチメイドと評した方がいいのか。どちらにしろ、クールを売りにしてるはずの彼女が、この服装をまとっているだけで違和感があった。本人もそれには気づいているのだろう。頬を紅潮させ、視線を落としている。 まぁ一部の人には、それが溜まらないと思うのかもしれないが。 そのオーソドックスなメイド姿をしている彼女にも、ひとつだけ普通のメイドとは違う装備があった。 それは一振りの魔剣。昔から邪美が使用している愛用の剣だ。かつてはこれで世界を救ったこともある。 この剣そのものは、邪美の魂ともいえるもの。普段の生活ではさすがに画しているが、ひとたび何かあれば、必ず邪美の右手に握られていた。しかし今のメイド姿にはあまりにも似つかわしくないものであった。 「な……何で……」 ふと邪美がつぶやく。 「何でこんなことに……っ!」 話は1週間前に遡る。 詳しい経緯を説明するとかなりの長さになるので省略するが、邪美が昔からの親友である紀伊呂華敏の呼び出しに応じたのが、そもそもの誤りだった。 華敏は言葉巧みに邪美を酒の席に連れ出すと、さんざんに酒を飲ませた。元々酒には強くなかった邪美はあっという間に飲まれてしまい、翌日屈辱的なものを見せ付けられてしまうのである。 それは契約書。「Maid Fight」にメイドとして参戦するという内容のものだった。酒で酔いつぶれた合間に、華敏の口車に騙されて、朦朧とした意識の中で自らサインをしてしまったようだ。 当然、邪美は反論した。こんなものは無効だと。しかし口先で華敏に勝てるほど、邪美は口達者ではない。結果、押し切られてしまったのである。 「と! いうわけで、悪いけど邪美。大会は1週間後だからシクヨロ~」 「気軽に言うな! だいたい、これは国の代表としての参戦なんだろう? 前の大会とは違い、個人が出れるものじゃない! 参加できるわけないじゃないか!」 「あ、そのへんは大丈夫」 別の切り口から反論を始めた邪美に対しても、華敏は待ってましたと言わんばかりに意地悪そうに笑いながら、地図を懐から取り出した。 「ここ見て。インド洋あたり。……この西部に位置する島群があるでしょ? ここをセーシェル共和国って言うんだけど……この国代表だから」 「はぁ?」 「首都がヴィクトリア。人口8万人くらいの小さな国ね。……あ、昔国際電話詐欺があった時に、この国につながるという点で有名かも」 「いやそーじゃなく! 何でこの国代表なんだ!? 国籍もないぞ!」 「私ら化人や魔女に、国籍なんてないでしょうに。……それに世界の大国相手に勝てるかもしれないと売り込んだら、喜んですぐに国連に参加し、参戦権を用意してくれたわよ、セーシェルの偉いさん」 「…………」 「国も公的に認めてくれたし、私も契約したってわけで。万事解決じゃない」 けらけら笑う華敏。この日、もう何度目か数えるのもあきらめた邪美がため息をつく。 「で、さ」 そこで華敏はひとつ間をおいて、次の言葉を紡ぎだした。 「当日は私達が用意した格好で来て欲しいわけ。契約書にもそのこと書いてあるけどね」 「私……達?」 「そ。このアイデアはある助っ人からいただいたものなのよ。……というわけで、助っ人さん、どうぞ~」 華敏の軽い口調とともに、奥から現れたのは、邪美がよく知る人物だった。 「……さ、桜子……?」 「いやーあっはっはっはっ。まんまと引っかかったね、邪美」 紅孔雀桜子。邪美の妹分の一人で、邪未と同じく魔女の血を引く。魔獣召喚のスペシャリストで、性格は快活明朗。その性格プロフィールのままの笑みを浮かべながら姿を見せた。 「まさか、あんたが一枚かんでたとはねぇ……」 「ふふっ、邪美。アタシは表もあれば裏もある女なのよ。いつまでもあんたの味方じゃない……」 「……とか言いつつ、単に『面白そうだから』という理由で手を組んだわけじゃないわよね?」 「あはは、さすがは邪美。よくわかってるぅ~」 またも深いため息をつかざるを得ない邪美だった。 「そんなわけでぇ」 会話の徒切れをつかみ、華敏が再び口を開いた。 「桜子のアイデアを元に、この私が腕をふるって仕上げた当日のコスチュームよ! 御覧なさい!!」 そしてご丁寧に用意してあった幕カーテンをひっぺがし、その奥にあったコスチュームを披露した。 そこにあるのは、例のメイドドレス。 「…………あ、あの……華敏さん……。これはいったい……」 「何って、メイド服。せっかくメイドファイトとかいうタイトルがついてるわけだし、格好はメイドじゃないとね~」 「………………」 「喜びなさい、邪美。世界でも有数のデザイナーである私が、これだけに集中しデザイン、作成したわけなんだから! そんじょそこらのブランド物とは桁が違うわよ~。桁が」 「………………」 発する言葉もない。ただ邪美はその場にへたりこんでしまっていた。 そして1週間後の本日に時が戻る。 何のかんのと抵抗をし続けた邪美であったが、華敏と桜子の二人相手では口では勝てず、結局用意されたメイド服で来る羽目になったのである。 力づくで抵抗するなり、当日すっぽかすという選択肢もあったのだが、それをしなかったというより思いつかなかったあたり、邪美の生真面目さがうかがえるところだった。 「お、いるいる。きちんと着てきたな。よしよし」 そんな「もう死にたい」オーラが出まくってる邪美に、後から現れた華敏たちが声をかけた。 「さすが私がデザインした世界で一着のメイド服。よく似合ってるわよ~」 「うぉ、これは……。我が姉貴分ながら、破壊力あるなぁ。いろいろな意味で」 「……殺スゾ、二人トモ……」 満面の笑みを浮かべる華敏と、ちょっと引いている桜子。その二人に対し殺意を向ける邪美であった。 「ところで」 そこでふと邪美は口を開いた。 「大会ルールを読んでみると、この大会はご主人と呼ばれる人物と一緒に参戦しないといけないようだが……これはお前がするのか?」 「いいや。……それも考えたんだけどねー。私が主人役で出てもいいんだけど、その場合、あまり乗り気じゃないあんたが私を逆に攻撃して、早々に1回戦負けを目論むような気がしてさ」 「……考えもしなかったな。その手があったか」 「……あんたの生真面目さのおかげで、私は今も生きていけるんだと実感できたわよ……」 きょとんとして答える邪美に、何か自分の腹黒さを示されたようで釈然としない華敏。 だが気を取り直すと、後ろに隠すようにつれていた少女を前に差し出した。 「というわけで、この子がご主人様役をやってくれることになったから。この子なら、あんたも全力で守ろうという気になるだろ?」 「へ……蛇姫!?」 おずおずと姿を現したのは、ショートカットの繊細そうな美少女、鬼流院蛇姫だった。 桜子と同じ邪美の妹分にして、魔女の一人。魔弾を扱う彼女だが、実は心優しく、邪美に付き従う大人しい女の子である。 「まさか、蛇姫まで一枚かんでたとは……」 「ち、違うんです! お姉様!」 「そーだよ。蛇姫の名誉のために言っておくと、あんたと同じ手口でやられたようなもんだから、蛇姫は」 慌てて否定する蛇姫に、横から桜子がフォローを入れる。どうやら蛇姫も華敏と桜子の口車に乗せられたようなのだ。 「く……卑怯な、華敏! 桜子!」 「狡猾とお言い!」 「……いや、それもっと悪いから、華敏さんよ……」 「その突っ込みナイスよ、桜子。――というわけで、邪美、蛇姫。頑張りなさいね」 ひらひらと手を振る華敏。邪美はまたも盛大にため息をついた。 「まぁ、前のような世界の危機があるわけでなさそうだし、命の危険性はないと思うが……。しかしいいのか? 蛇姫。こんなものにつきあわされて」 「私は……確かに争いごとは嫌いですし、何よりお姉様にご迷惑をおかけするのは本心ではありません。ですが――」 「ですが?」 「――でもやっぱり、お姉様とまた一緒に戦える……それは少しだけ望みでもあるんです。一緒に喜びを分かち合いたい……こんなことを考えてるわがままな妹なんです。蛇姫は」 「……ふっ」 蛇姫の少し困惑しながらも、それでも少し喜びをにじませた言葉に、この日初めて、邪美は表情を崩した。 「相変わらず頑固だな、お前は」 そして彼女の頭を優しく撫でる。蛇姫は少し頬を紅潮させ、照れながらも優しげにはにかんだ。 「仕方ない。蛇姫がそう言うなら、つきあうさ。確かに悪くない」 「じゃ、話は決まりね」 そう言いながら、華敏は心の奥底でほくそ笑んだ。 ――やはり、この二人を組み合わせたのは最上の方法だったと。 我ながら、何か腹黒くなったような気もしない華敏であったが、今は気にしないようにした。きっと人間界に定住するようになったせいなのであろう。うん。 「よぉ~し、この勢いで優勝しろ! 伏魔殿邪美」 「……と、ちょっと待て、華敏」 勢いを殺ぐかのように、華敏の掛け声を遮って、邪美は前から抱いていた疑問を投げかけた。 「何でこの大会に参加しようとした? お前にとって、世界の勢力争いなぞ興味はあるまい?」 「ん~?」 「何故わざわざそんな小さな島国に力を貸そうとするのだ? 何か裏があるんじゃないのか?」 実は話を聞いたときから抱いていた疑問だった。その場で問い詰めようとしたのだが、あまりのショックと、さらにメイド服を見せられとどめとなり、茫然自失のあまり聞き損ねていたのだ。 「確かに政権には興味ないわね。私が興味があるのはこっちの方」 そう言って、華敏は大会ルールが載ってる冊子の一番最初のページのある文章を指差した。そこには「優勝した国家はそれから次回のMaid Fight開催までの4年間、国連の代表となると同時に、次回のMaid Fightの主催国となる」とあった。 「主催国になれば、ある程度のルールの改変もできそうじゃん。何せ国連の主導権を得るわけだし。そうすれば……あの大会をもう一度蘇らせることもできるってわけよ」 「まさか……華敏、お前!?」 「そう、ZFの復活……。第1回大会で白き闇が出てきたばかりに、すべてなくなってしまったあの大会を復活させることができるはず」 そう言って、華敏は寂しげな瞳を空に向けた。 「そしたら……また会えるかもしれないんだよ。私のオトモダチに……」 「華敏……」 複雑な過去を持つ華敏。その事情は邪美も知っている。 このとき初めて、邪美はどうしてここまで強引に華敏が事を進めたがるのか理解できた。 「ま、それに。また懐かしい顔にも会いたいじゃない?」 「――わかったよ、華敏」 照れ隠しに違う言葉を紡ぐ華敏に、邪美は真摯な瞳を向けた。 「どこまでできるかわからないが……行けるところまで行くさ。約束する」 「ああ、頼むよ。不敗の魔女、伏魔殿邪美」 華敏が右手を差し出した。邪美は少し笑みを漏らすと、ためらいもなくその手を叩く。お互いにパアンと鳴らした手の音が、蒼穹の空に響いた。 しばらく無言で見詰め合っていたが、邪美は背中を向けた。 「じゃ、受付を済ませてくる。しばらく待っててくれ。……行くぞ、蛇姫」 「あ、はい。お姉様!」 邪美は蛇姫を引き連れ、その場を立ち去っていく。 その後姿を見ながら―― (……というのは表向きの名目で。まぁ本心っちゃ本心なんだけど……。2割くらいはあんたのメイド姿を見たかっただけ……とか言ってたら、さすがに魔剣で殺されてたのかなぁ……) ……ふとこんなことを考えつつ、隠してたニヤニヤを口元に浮かべた華敏であった……。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ご主人様 鬼流院蛇姫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||