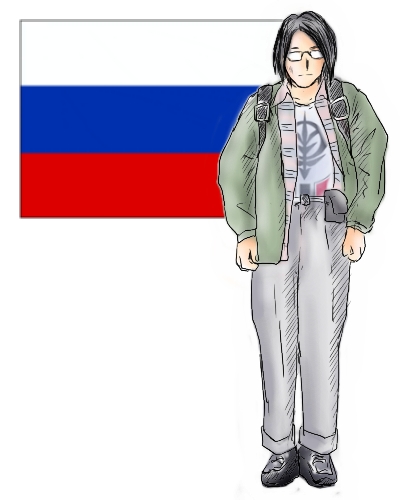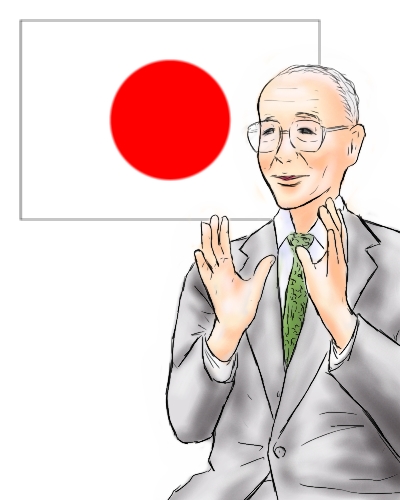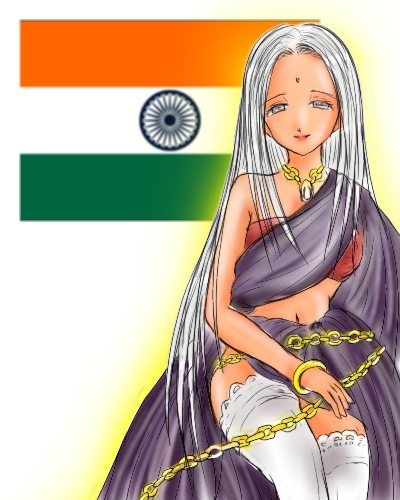中国代表 桂花  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国。 人口数世界一を誇る大国・・・。 この国にその名を知らぬものはいない、といわれている会社があった。 超軍事会社「先行社」・・・。 この国の軍備はいまやこの会社が手中に収めているといっても過言ではないだろう・・・。砲身を作っていただけの小さな会社だったがわずか一、二年での業績の急成長たるや、飛ぶ鳥どころか神話に登場する龍ですら落としてしまいそうな勢いだ。 この会社が急成長をとげた理由・・・、それは実にシンプルだった。 軍の欲しい物をどこよりも安く、また早く作るところにある。それでいて、最新鋭の軍装備ときているから軍部は他には目もくれずこの会社にべったりなのだ。 「では、その装備は明日にでも納品しましょう。」 「おおお、さすが金社長。話が早くて助かる、これからもよろしく頼みますよ」 軍の司令室で細身のスーツ姿の男と小太りの軍服の男が握手をかわす。 では、と会釈をしスーツの男が部屋を出る。 部屋の外にはチャイナ服の少女が頬を膨らませて待っていた。 年の頃12,3の外見。髪はポニーテールで肩口ぐらいの長さ。身長は140ぐらいか。スリーサイズは・・・あえてかたるまい。 「なーがーい!」 チャイナ服の少女はスーツの男を見上げると口をとがらた。 「だからいったろ、桂花。来てもつまらないって」 スーツ姿の男が少々あきれた顔で、またか、といった感じでため息をつく。 「むー。でも桂花は遼斧のメイドだから一緒にいたいの・・・」 スーツの端を握り、うつむく桂花。 スーツ姿の男、金 遼斧はうつむく桂花の頭を優しくなでた。 「そろそろ、帰ろうか」 「・・・うん!」 桂花は頭をなでてもらったのがうれしかったのか、途端に元気になった。 にこ、と笑顔を見せて司令室から駐車場へと続く廊下を無邪気に走り回る。 それを見て、遼斧も自然と笑顔がこぼれるのであった。 ずいぶん遠くで桂花が手を振って遼斧を呼ぶ。 桂花が曲がった廊下の角でどん、と何かにぶつかった音が遼斧に聞こえた。 「!、大丈夫か、桂花!」 走り出した遼斧の耳に男の声が聞こえる。 「いたいじゃないか、おじょうちゃん。曲がり角を曲がるときはきをつけないと大変なことになるって習わなかったのかい?」 「よせ!」 走りながら遼斧は叫んだ。 「保護者がいるのか。あんたの代わりに社会的指導をおれがやってやるよ!」 男の下卑た笑い声が廊下に響き渡る。 「やめろ、やめるんだ、桂花!」 遼斧が叫ぶと同時に男の笑い声がやむ・・・。 遼斧が廊下の角についたとき、そこには血まみれの桂花と元、人だった大量の肉と血が散乱し悪臭を漂わせていた。 「桂花!」 遼斧が血だまりを介せず桂花に近寄る。 「ゴ、シュ・・・ジンサ・・・マ」 先ほどまでとは打って変わり焦点の合わない目で遼斧を見上げる。 「く、やはり。ぶつかった衝撃で〔自動戦闘モード〕に切り替わっている!」 遼斧は桂花を抱えあげると足早に車へと向かった。 「・・・ん」 「よかった、意識が戻ったね」 桂花が目を覚ますと見慣れた彼女の部屋の天井が目に入った。 「むー、遼斧、桂花また・・・」 桂花は天井に視線をやったまま遼斧に問いかける。 「・・・ごめんな、桂花。僕が気をつけていれば・・・」 遼斧は桂花の手をぎゅっと握る。 「・・・いいの、遼斧。それが桂花が作られた理由だし」 桂花は、その上にそっと手を重ねる。 「・・・」 「桂花もでるんでしょ、例の大会」 桂花は体を起こし遼斧を見つめる。 「・・・性能テストにはうってつけの場所なんだ。けど・・・」 遼斧は言いよどむ。 「うー、桂花負けないから兵器だもん!」 えへん、と胸をはる桂花。 「・・・そうだな、僕の作った桂花が負けるわけないか!・・・よし!」 遼斧は決意をこめて桂花を見つめ返す、桂花はコクッとうなずいた。 こうして中国からヒューマノイドタイプメイド〔桂花〕が名乗りを上げた 「桂花、公の場ではちゃんとご主人様っていうんだぞ」 「うん、遼斧!」 「・・・だいじょぶかな」 先行社研究室。 天井から細部をも照らし出すような光が注ぐ中、遼斧を筆頭に数人の研究者が一所に集まり作業をしている。 「神経接続、循環器ともに良好」 「彼女の心臓部は?」 「予定通りに機能しています」 「そうか、では後は・・・彼女のメインコンピュータに作成情報を入れて・・・、よし」 ヴ・・・ン。 「う・・・」 研究者たちの集う中心にある人型のロボットが誕生の産声をあげる。 「やった、成功だ」 「やりましたね、社長」 「・・・ああ」 研究者たちが歓喜の声をあげる中、一人遼斧はほっと安堵の息を漏らす。 ロボットに視線をやるとこちらを見上げ、 「・・・リョウ・・・フ」 かわいい少女のなりをしたロボットが遼斧を見てつぶやく。 「そうだよ、僕は遼斧だ。・・・桂花」 目を細め、慈しむように桂花の頭をなでる。 桂花誕生から二週間後・・・ 社長室にいる遼斧の下に研究者の一人がやってきた。 「そうか、では順調に性能テストをクリアしていっているわけか」 椅子に腰掛け書類に目をとおしながら遼斧は相槌をうつ。 「はい。しかし、この最後の項目がネックとなってまして・・・」 研究者が手にした資料を遼斧の机に差し出す。 「なるほど・・・。不慮の事故などで桂花の記憶回路が断線してしまったときに切り替わる”自動戦闘モード”か」 「はい、何しろ単機でこのビルを5分で平地にできるスペックをつんでますですので・・・加えてまだ外装が完了してませんのであまりに衝撃に弱く・・」 「そうだな・・・、とりあえず僕が”自動戦闘モード”にパワーオートセーブ機能をつけ出力を落としておくからその後に性能テスト、というかたちにしようか。外装は手抜きになってはいけないからあまり技術部をいそがせるなよ?」 「わかりました、ではそのように伝達しておきます。あ、それとですね社長・・・」 退出しようとした研究者が思い出したように手を叩く。 「実は桂花が社長に会いたいと、駄々をこねてまして・・・。」 「そうか、そういえば桂花が作られて忙しさにかまけて会いにいってなかったな」 そうだな、遼斧は思った。 久しぶりに愛娘に会うとするか。 「やあ、桂花。どうだい、調子は?」 研究施設内の一室、桂花のネームプレートのある扉をノックし遼斧が中に入る。 「あー、遼斧!」 桂花は遼斧が入ってくるや否や飛びついた。 「ごめんな、さびしかったかい?」 遼斧は桂花の頭を撫でる。 「うん、さびしかったよ・・・遼斧」 遼斧をつかむ手にわずかに力がこもる。 「・・・そうか、でももう心配ないぞ」 「?」 「今日の調整が済んだら僕とずっと一緒にいられるからね」 「・・・ホント?」 桂花が遼斧を見上げる。 「ああ、本当だよ」 「!!」 わーい!と全身で喜びを表現する桂花。 その様はまるでロボットを思わせない。 動き、仕草、感情そのどれもが年相応の少女を思わせた。 (うまく仕上がってる・・・。後は今日の調整次第か) 桂花を見ながら遼斧は思考をめぐらす。 「じゃあ、そろそろ行こうか桂花」 遼斧は桂花に手を差し出す。 「うん!」 桂花は差し出された手をぎゅっと握り遼斧とともに部屋を後にした。 「どうだ?」 「はい、パワーオートセーブ機能は働いているようです」 「・・・よし、では実験を開始する。試作型のパワーを同程度に抑え、桂花の自動戦闘モード状態のデータを収集するぞ」 モニタールームから遼斧が指示をだす。 実験場で待機している桂花の前に試作型が運び込まれる。 試作型も桂花同様、人型のロボットである。 しかし、稼動部や骨格がむき出しの上、顔にはカメラを置いてあるだけのそれはまさに試作型だった。 「では、実験開始」 遼斧合図とともに二体が稼動を始める。 先に動いたのは試作型だった。桂花めがけて間合いをつめる。 一方の桂花にはまだ動きがない。 試作型が桂花に殴りかかる。しかしやはり桂花は微動だにしなかった。 試作型は桂花の顔面にパンチをヒットさせた。 衝撃音とともに桂花が実験室の壁まで吹っ飛ばされ壁にめり込む。 「社長、桂花が・・・」 モニターを見ていた研究員の一人が心配そうに声を上げる。 「桂花は大丈夫だ、問題は・・・」 遼斧がつぶやく。 モニター画面が桂花を映す、彼女は壁にめり込んだ体を起こしゆっくりと敵を視認した。 桂花が動いているのを確認し、試作型が桂花へと再度間合いをつめる。 試作型が再度殴りかかってくる。 ギィン・・・! 実験場に鋭い金属音がこだまする。 桂花の一撃により腕を残し四散した試作型の無残な姿、一方の桂花は無傷・・・。 「抑えてこれほどのパワーを発揮するとは・・・」 研究員の一人がごくり、とつばを飲み込む。 「やれやれ、とんだじゃじゃ馬娘を作ってしまったな」 ふう、と遼斧がため息をついた。 「目を離さないように注意しないと危険だなあ」 一般的な親の気持ちとはまるで反対の心配をする遼斧であった。 この後何度か衝撃のたびに”自動戦闘モード”が発動し、遼斧をその都度東奔西走させる。 外装換装がすんでからは滅多に発動しなくなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ご主人様 金遼斧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||